なぜあなたのサイトはChatGPTに引用されない?LLMOの仕組みと対策を解説
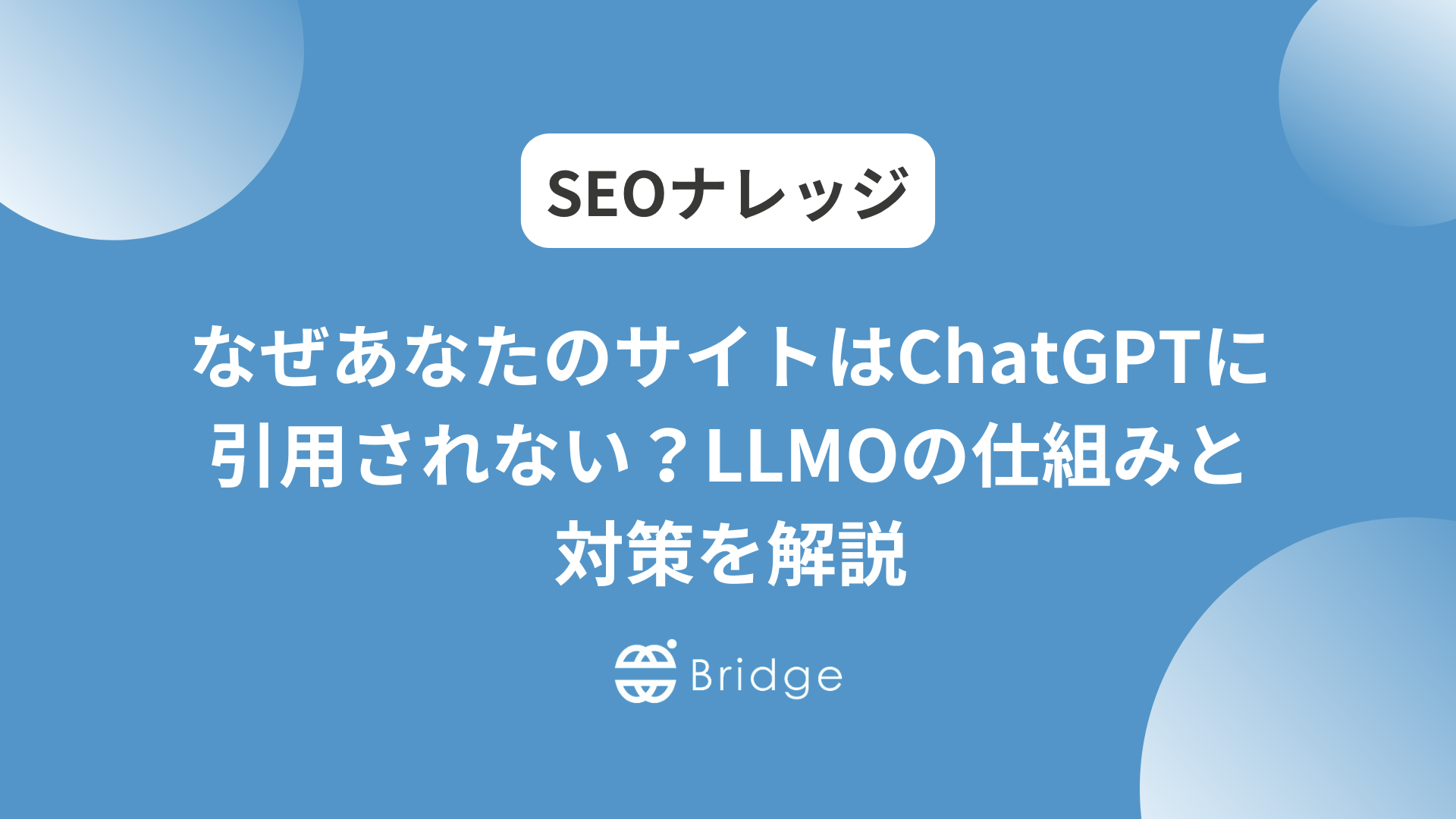
最近「LLMO」「GEO」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?
経験豊富なSEO担当者であるあなたが、「SEOと何が違うのか?」「結局、これから何をすればいいのか?」と疑問に思うのは当然のことです。
結論から申し上げると、LLMOは、これまで培ってきたSEOの知識を捨てるものではなく、進化させるものです。
この記事では、ChatGPTが情報を学び、引用する「仕組み」から解き明かし、明日から実践できる具体的なLLMO対策までを体系的に解説します。
【免責事項】
本記事に掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、特定のマーケティング手法の効果を保証するものではありません。特にLLMOにおいてはまだ不透明な部分が多く、AIおよび大規模言語モデルの技術は日々進化しているため、本記事の情報が常に最新であることを保証するものではありませんのでご了承ください。
この記事でわかること:
- ChatGPT等のLLMがどうやって情報を引用するかの「仕組み」(RAG)
- 従来のSEOとの本質的な違いと、これから活かせるスキル
- ChatGPT等のLLMに”選ばれる”コンテンツを作るための基礎から上級までの具体的な対策
この記事の監修者
坂本理恵 株式会社Bridge 取締役COO
▼主な経歴
- 株式会社リクルート、株式会社サイバーエージェント出身
- 株式会社Bridgeを創業し、SEO事業、インターネット広告代理事業の立ち上げ〜グロースに従事
- AI×SEO関連のウェビナーにも登壇
▼関連リンク
https://x.com/rie151515
目次
LLMOとは?ChatGPT時代の新たな最適化
💡このパートまとめ
LLMO(大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPT等のLLMに引用されやすいようコンテンツを最適化すること。
まず、この新しい概念「LLMO」の正体を正確に理解することから始めましょう。
LLMO(Large Language Model Optimization)の正式な定義
LLMOとは、Large Language Model Optimizationの略称です。日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳されます。
具体的には、「ChatGPTに代表される、大規模言語モデル(LLM)を搭載したAIチャットボットや、GoogleのAI Overviewsのような生成AI検索の回答に、自社のコンテンツが情報源として引用・参照されやすくするための最適化プロセス」全般を指します。
これまでのSEOが「検索エンジンのランキングで上位表示される」ことを目的としていたのに対し、LLMOは「LLMの回答に引用される」ことを目指す、新しい時代の最適化思想なのです。
なぜ今LLMOが注目されているのか?検索行動の変化
LLMOが注目される背景には、ユーザーの検索行動の根本的な変化があります。
これまでのユーザーは、キーワードで検索し、表示された10本の青いリンクから、自分で正解を探しにいっていました。しかし、ChatGPTや生成AI検索の登場により、ユーザーはLLMに直接「質問」を投げかけ、LLMが要約・生成した「答え」を最初に受け取るようになります。
この「LLMが生成する答え」に自社の情報が含まれなければ、ユーザーに認知される機会そのものが失われてしまう可能性がある。だからこそ、LLMOに注目が集まっているのです。
GEO(Generative Engine Optimization)との違いは?
LLMOと非常によく似た言葉に「GEO(Generative Engine Optimization)」があります。現時点では、この二つの言葉はほぼ同義で使われることがほとんどです。あえて違いを言うならば、LLMOが最適化の対象である「LLM」という技術そのものに焦点を当てているのに対し、GEOはLLMが回答を生成する「エンジン(検索エンジンやチャットボット)」というプラットフォームに焦点を当てた言葉、という程度のニュアンスの違いです。本記事では、両者をほぼ同じ概念として扱います。
【仕組みから理解】ChatGPTはどのように情報を学び、引用するのか?
💡このパートまとめ
LLMは過去データで「学習」し、RAG技術で最新情報を「検索・引用」して回答を生成している。
LLMO対策がなぜ有効なのかを理解するには、ChatGPTのような現代のLLMがどうやって答えを作っているか、その「思考プロセス」を知る必要があります。専門的になりますが、非常に重要なので分かりやすく解説します。
ChatGPTを始めとするLLMは『閉じた図書館(過去の学習データ)で勉強した秀才』のようなものです。しかし、最新の話題について聞くと『開架図書(Web)を数冊参照して要約する』という動きをします。私たちが最適化すべきは、この”開架図書”に選ばれることなのです。
この動きは、大きく2つのフェーズに分かれています。
フェーズ1:膨大なデータによる「事前学習」
まず、LLMは開発段階で、インターネット上の膨大なテキストや画像データ(Wikipedia、ニュース記事、ブログなど)を読み込み、単語の関係性や文法、世界の常識といった言語のパターンを「学習」します。これにより、LLMは人間のように自然な文章を生成する能力を獲得します。
ただし、この学習データはある特定の時点(ナレッジカットオフ)で固定されているため、これだけでは最新の情報について答えることはできません。
フェーズ2:RAG(検索拡張生成)による「引用」
そこで使われるのがRAG(Retrieval-Augmented Generation / 検索拡張生成)という技術です。これは、ユーザーから質問を受けた際に、以下の3ステップで回答を生成する仕組みです。
- Retrieval(検索・取得): ユーザーの質問に関連する情報を、リアルタイムでWeb検索などを実行して探し出す。
- Augmented(拡張): 見つけ出した最新かつ信頼性の高い情報を、元の質問に追加情報(文脈)として付け加える。
- Generation(生成): 質問と、追加された最新情報を基に、最終的な回答文章と引用元を生成する。
結論:だからこそ「引用されやすい」コンテンツが重要になる
つまり、LLMOとは、このRAGのプロセス、特に最初の「検索・取得」で選ばれやすく、次の「生成」で的確に要約・引用してもらうための最適化活動に他なりません。この仕組みを理解することが、効果的な対策を立てる上での羅針盤となります。
LLMOは新しいSEOか?同じ点と3つの決定的な違い
💡このパートまとめ
LLMOはSEOの原則が土台。ただし、最適化対象、評価基準、最適なコンテンツ形式が異なる。
LLMOの登場でSEO対策は不要になるのではと一部では騒がれています。しかし私の見解では逆です。RAGの仕組みを理解すれば、E-E-A-TなどSEOの本質を理解している人ほど、LLMOにスムーズに対応できることがわかるはずです。
共通の土台:高品質で信頼できるコンテンツという原則
SEOの本質が、ユーザーの検索意図に答え、高品質で信頼できるコンテンツを提供することにあるように、LLMOの根幹も全く同じです。RAGプロセスにおいても、LLMは信頼でき、権威のある情報源を優先的に参照します。あなたが培ってきた、価値あるコンテンツを創出するスキルは、LLMOの時代において、より一層重要になります。
比較表で見るSEOとLLMOの違い
違いは、最適化する「対象」にあります。SEOが機械的な「検索アルゴリズム」を相手にしていたのに対し、LLMOは、より人間に近い文脈理解能力を持つ「RAGプロセスとLLM」を相手にします。
| 項目 | 従来のSEO | LLMO |
|---|---|---|
| 最適化対象 | 検索エンジンのアルゴリズム | RAGプロセスと大規模言語モデル(LLM) |
| 主な評価基準 | キーワード、被リンク | 文脈、E-E-A-T、引用のしやすさ |
| 最適な形式 | 網羅的な記事 | 会話型、Q&A形式 |
これまでのSEO知識は、無駄になるのか?
結論、全く無駄にはなりません。むしろ、LLMOはSEOの延長上にあると言えます。
キーワード選定、検索意図の分析、E-E-A-Tの向上といったSEOの基本スキルは、LLMOにおいても必須の土台となります。LLMOとは、その土台の上に、LLMと対話するという新しい読者の行動を理解し、それに合わせたコンテンツの「表現方法」を加えていく、いわばSEOの進化形なのです。
ChatGPTに引用されるコンテンツへ!今日から始めるLLMO基本対策5選
💡このパートまとめ
E-E-A-Tの強化、会話型コンテンツへの転換、構造化データの実装などが具体的な対策になる。
ChatGPT等のLLMの仕組みを理解した上で、具体的な対策を見ていきましょう。今日から始められる5つの基本的なアクションプランです。
対策①:E-E-A-Tを再定義する(RAGの検索で選ばれるために)
RAGプロセスで信頼できる情報源として選ばれるためには、LLMが理解できる形でE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を示すことが重要です。
- 著者情報を明確にする: 専門的な知見を持つ著者のプロフィールを明記する。
- 運営者情報を構造化する: 企業や組織の公式サイトであれば、その情報を構造化データでマークアップする。
- 権威あるサイトからの引用・言及を増やす: 第三者からの評価によって信頼性を示す。
対策②:一つの問いに一つの答えを返す「Q&Aコンテンツ」を作る(LLMが要約しやすくするために)
LLMは「質問」に対して「回答」を生成します。コンテンツ自体が明確なQ&A形式になっていると、LLMはその部分を引用しやすくなります。「〇〇とは?」という見出しに対して、その直下で「〇〇とは、〜です。」と端的に結論を述べる「一問一答」の構造を意識しましょう。
対策③:自然言語での検索を意識した「会話型コンテンツ」を増やす
ユーザーはLLMに話し言葉で質問します。「SEO 対策」ではなく、「ブログのアクセス数を増やすには、具体的に何をすればいいですか?」といった形です。このような話し言葉の質問(自然言語クエリ)を記事の見出しにし、それに答えるコンテンツを作成しましょう。
対策④:構造化データでLLMにコンテンツの意味を正確に伝える
構造化データは、LLMがページ内容を正しく理解するための「意味のラベル」です。例えば、FAQコンテンツにFAQPageスキーマを設定すると、LLMは「これが質問で、これが答えだ」と正確に理解できます。
対策⑤:権威ある情報源として「引用される」一次情報を目指す
最も本質的な対策は、自らがその分野における一次情報源になることです。独自の調査レポート、業界のトレンド分析、自社だけの成功・失敗事例などは、LLMにとっても価値の高い学習データとなり、結果的に引用・参照されることに繋がります。
【上級編】ChatGPT等のLLMの仕組みから逆算したLLMO戦略4選
💡このパートまとめ
LLMの学習と引用の仕組みに合わせ、エンティティの確立や情報の部品化で引用確率を最大化する。
ここからは、一歩進んだテクニックです。単に記事を作るだけでなく、LLMの「思考」そのものに影響を与え、自社をその分野の第一人者として「認識させる」ための戦略的アプローチをご紹介します。
《学習フェーズへの対策》戦略①:エンティティSEOの徹底
Google検索やLLMは、もはや単なるキーワードではなく、「エンティティ(意味を持つ概念)」とその関係性をまとめたデータベース(ナレッジグラフ)を基に世界を理解しています。
LLMの「事前学習」は、このエンティティ間の関係性を学ぶプロセスです。したがって、自社名や製品名を、特定の専門分野と強く結びついた「権威あるエンティティ」としてWeb上で確立できれば、LLMの学習データ内で「このテーマについて信頼できる情報源」として認識されやすくなります。これは、LLMの「教科書」に載るための長期的なブランディング活動と言えます。
具体例:会計ソフト「Cloud会計」の場合
- 悪い例: 「経費精算 システム」というキーワードで、機能紹介の記事を量産するだけ。
- 良い例:
- 自社サイトで創業者(会計士)の実名を出し、プロフィールを詳細に記述する。
- 業界専門誌に「Cloud会計の専門家が語る、インボイス制度の注意点」といったテーマで寄稿する。
- Wikipediaに自社の客観的な情報が掲載されるよう、信頼できるメディアでの言及を増やす。
→これにより、LLMは「Cloud会計」というエンティティを、単なる製品名ではなく「会計の専門家集団が提供する、信頼できるサービス」と学習します。
《学習フェーズへの対策》戦略②:リンクに頼らない「Web上の評判」を形成する
LLMの「事前学習」では、Web上のあらゆるテキストが学習対象になります。その際、ハイパーリンクがなくても、特定の固有名詞(ブランド名など)が、どのような言葉と共に語られているか(共起関係)を大量に学習し、そのエンティティの「評判」を形成します。
口コミサイトやQ&Aサイト、SNSなどで、自社ブランドがポジティブな文脈で「言及(サイテーション)」される機会を増やすことが、LLMのブランド認識を良好に形成する上で必要になってくると言えます。
具体例:
LLMは、Web上で以下のような文脈を発見した場合、貴社への「評判」を形成していきます。
- Q&Aサイトでの言及: 「〇〇の業務改善なら、株式会社△△のツールが一番使いやすかったですよ」
- 個人ブログでの言及: 「先日参加した株式会社△△のセミナー、非常に勉強になった」
- ニュースサイトでの言及: 「市場調査会社のレポートによると、この分野では株式会社△△がトップシェアを誇る」
→リンクがなくても、こうしたポジティブな文脈での言及が増えることで、LLMは「株式会社△△ = この分野で評判の良い会社」と学習する可能性が高まります。
《RAG引用フェーズへの対策》戦略③:「一見出し=一トピック」で引用されやすい部品を作る
前述したRAGの「検索・取得」プロセスは、質問に最も関連性の高いコンテンツの「断片(チャンク)」を探し出します。一つの見出しの下に複数のトピックが混在していると、特定の質問に対する関連性が薄まります。
逆に、「一つの見出しが、一つの問いに完璧に答える」ように設計されたコンテンツは、RAGプロセスで引用される可能性が高くなると考えられます。記事全体を、LLMが自由に引用できる「知識の部品箱」のように設計するイメージです。
具体例:「LLMOとは」をテーマにした記事の場合
- 悪い構成例(LLMが引用しにくい):
<h2>LLMOとSEO、そしてGEOとの違い</h2>
(この見出しの下で、LLMOの定義、SEOとの違い、GEOとの違いをまとめて解説してしまっている) - 良い構成例(LLMが引用しやすい):
<h2>LLMOとは?</h2>
<h2>LLMOとSEOの決定的な違い</h2>
<h2>LLMOとGEOの関係は?</h2>
→このようにテーマを細分化することで、「LLMOとは?」という質問に対しては最初の見出しが、「SEOとの違いは?」という質問に対しては次の見出しが、それぞれ最適な「部品」としてLLMに引用される可能性が高まります。
《RAG引用フェーズへの対策》戦略④:PREP法による記述の徹底
RAGプロセスの最後の「生成」フェーズでは、LLMが取得した断片を要約して回答を生成します。PREP法(結論→理由→具体例→結論)のように、結論が最初に書かれている文章構造は、LLMがその断片の要点を瞬時に把握し、正確に要約することを容易にします。
これは人間にとって分かりやすいだけでなく、LLMにとっても非常に「理解しやすい」論理構造です。ライティングレベルでの最適化として有効だと言えるでしょう。
まとめ:ChatGPT等のLLMOはSEOの延長線上にある
今回は、ChatGPTをはじめとするLLMに選ばれるための「LLMO」について、その仕組みから具体的な対策までを解説しました。
本記事の要点:
- LLMOはSEOの進化形: ChatGPTのようなLLMに引用されるための最適化であり、SEOの知識が土台となる。
- LLMの仕組み: LLMは過去データで「学習」し、「RAG」技術でWebを検索・引用して回答を生成する。
- 具体的な対策: 基本対策5選と、LLMの仕組みから逆算した上級戦略4選をまずは理解することが重要。
最後に、実務的な視点として一つ補足します。
LLMの世界は、私たちの想像を超えるスピードで進化しています。そのため、この記事で解説した見解が、数ヶ月後にはより新しい常識に変わっている可能性も十分にあり得ます。
では、今すぐ全てのSEOリソースをLLMOに振り分けたり、外部のコンサルタントに依頼すべきでしょうか? 私の見解では、その必要はまだありません。実際のクライアントデータを見ても、現時点でのLLMOが検索流入に与えるインパクトは、まだ限定的です。
したがって、今あなたが本当に集中すべきは、焦って個別の戦術に飛びつくことではなく、冷静に最新情報をキャッチアップし続け、自社としてこの変化にどう対応していくかの方針を議論しておくことです。
LLMOの波を恐れる必要は全くありません。むしろ、これまでやってきたSEOの土台が生きてくる、大きなチャンスです。
より具体的にChatGPTのLLMOについて相談したい場合はお気軽にお問い合わせください。
Pick up
SEOナレッジのピックアップ記事
-

#SEOナレッジ
SEO記事作成代行会社・サービス27選!依頼する際の選定ポイントも紹介
-
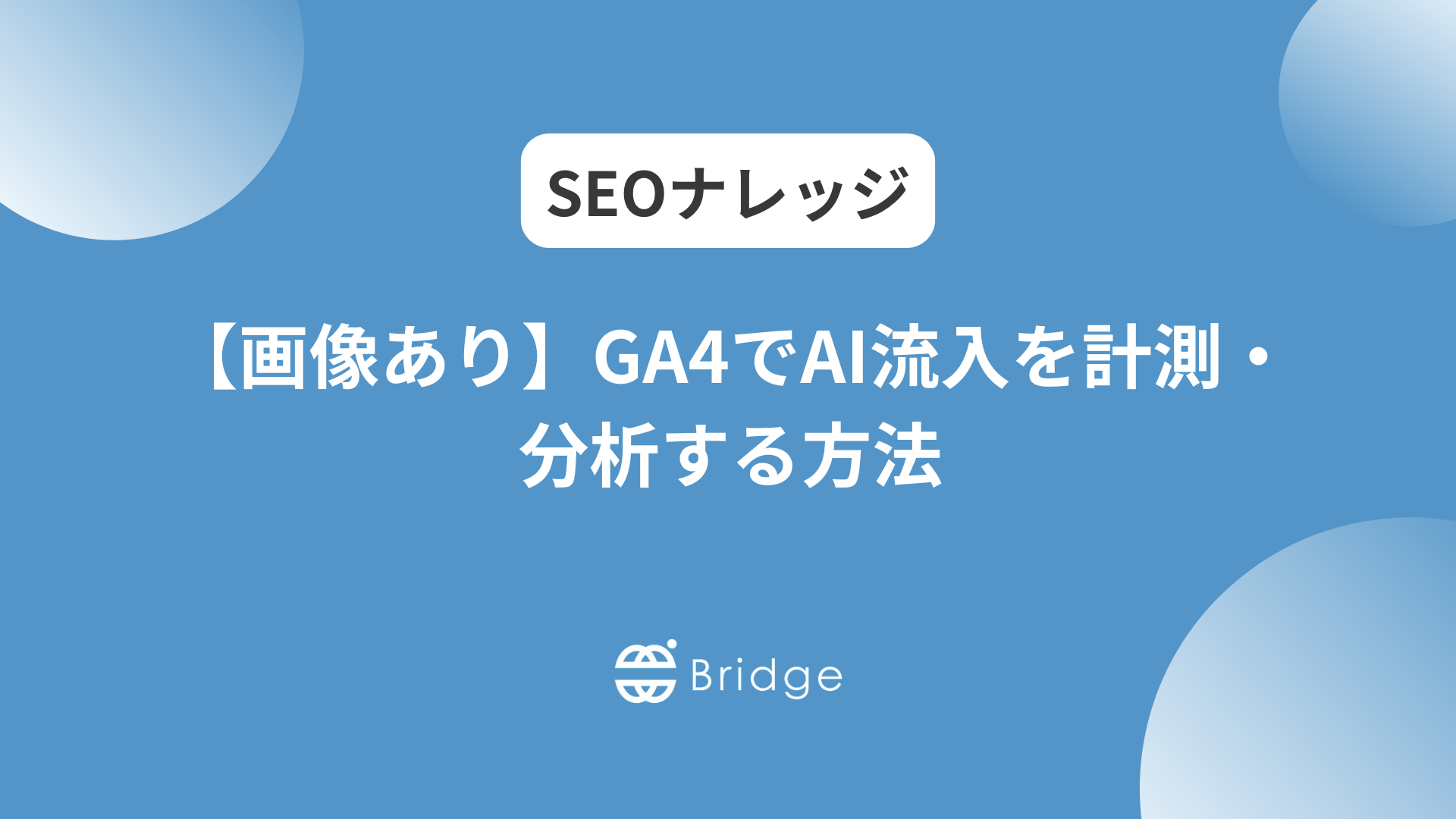
#SEOナレッジ
【画像あり】GA4でAI流入を計測・分析する方法
-

#SEOナレッジ
クエリファンアウトとは?Google AI検索の仕組みとSEOへの影響を解説
-
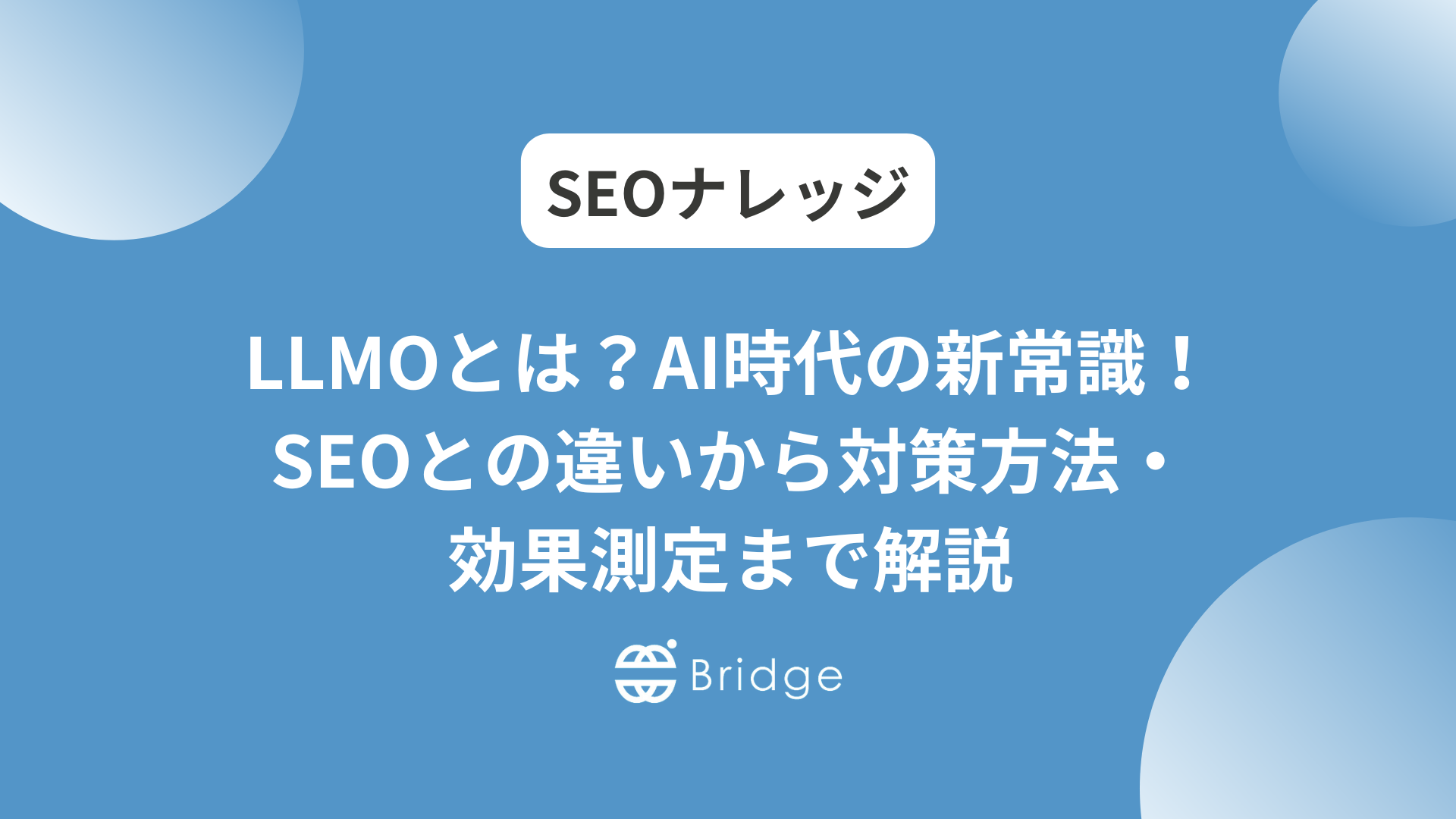
#SEOナレッジ
LLMOとは?AI時代の新常識!SEOとの違いから対策方法・効果測定まで解説
-
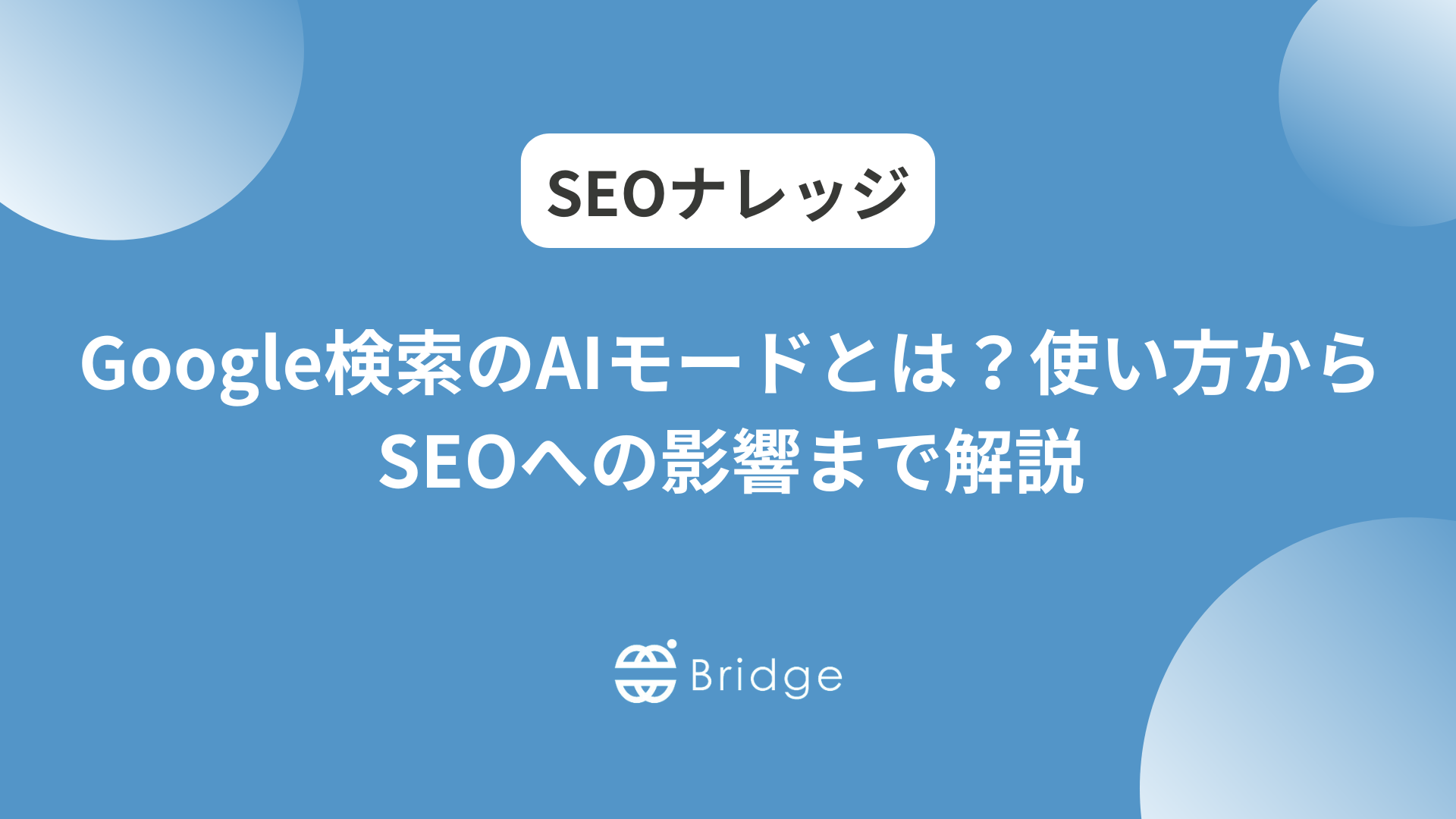
#SEOナレッジ
Google検索のAIモードとは?使い方からSEOへの影響まで解説
-
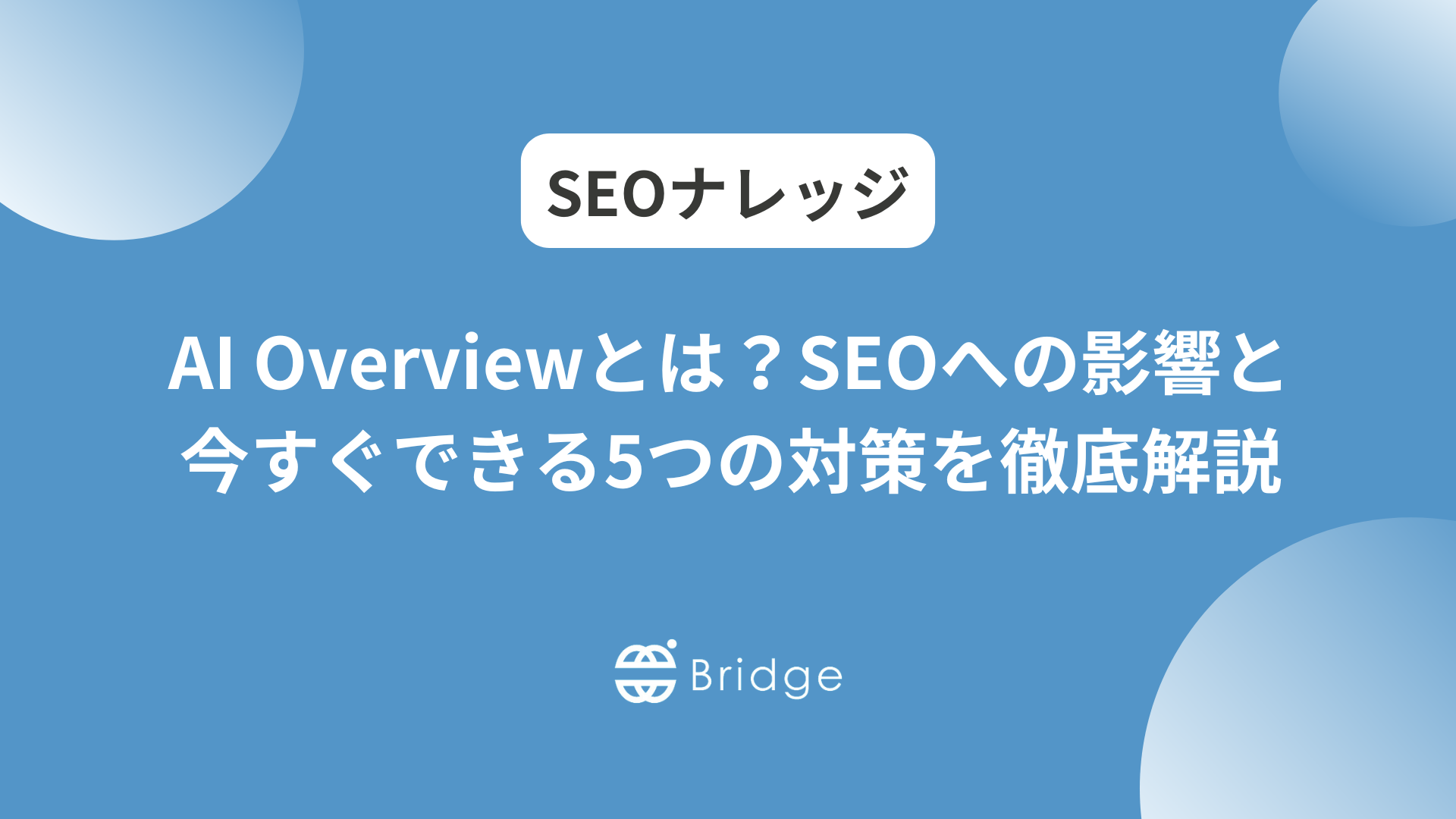
#SEOナレッジ
AI Overviewとは?SEOへの影響と今すぐできる5つの対策を徹底解説
-

#SEOナレッジ
AI記事作成ツール徹底比較|ChatGPT・Gemini・Claude、SEOに最適なのは?
-
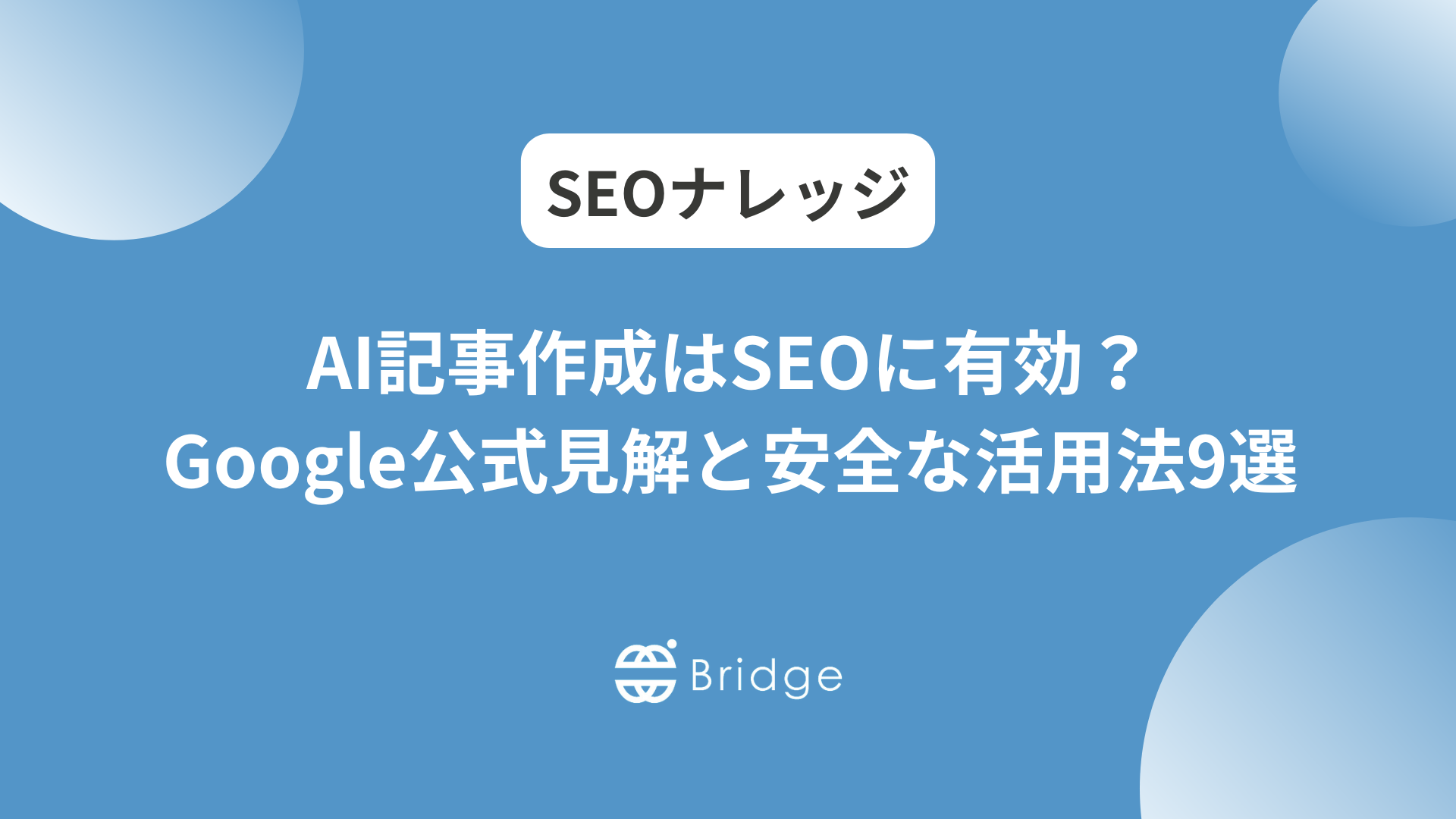
#SEOナレッジ
AI記事作成はSEOに有効?Google公式見解と安全な活用法9選
-
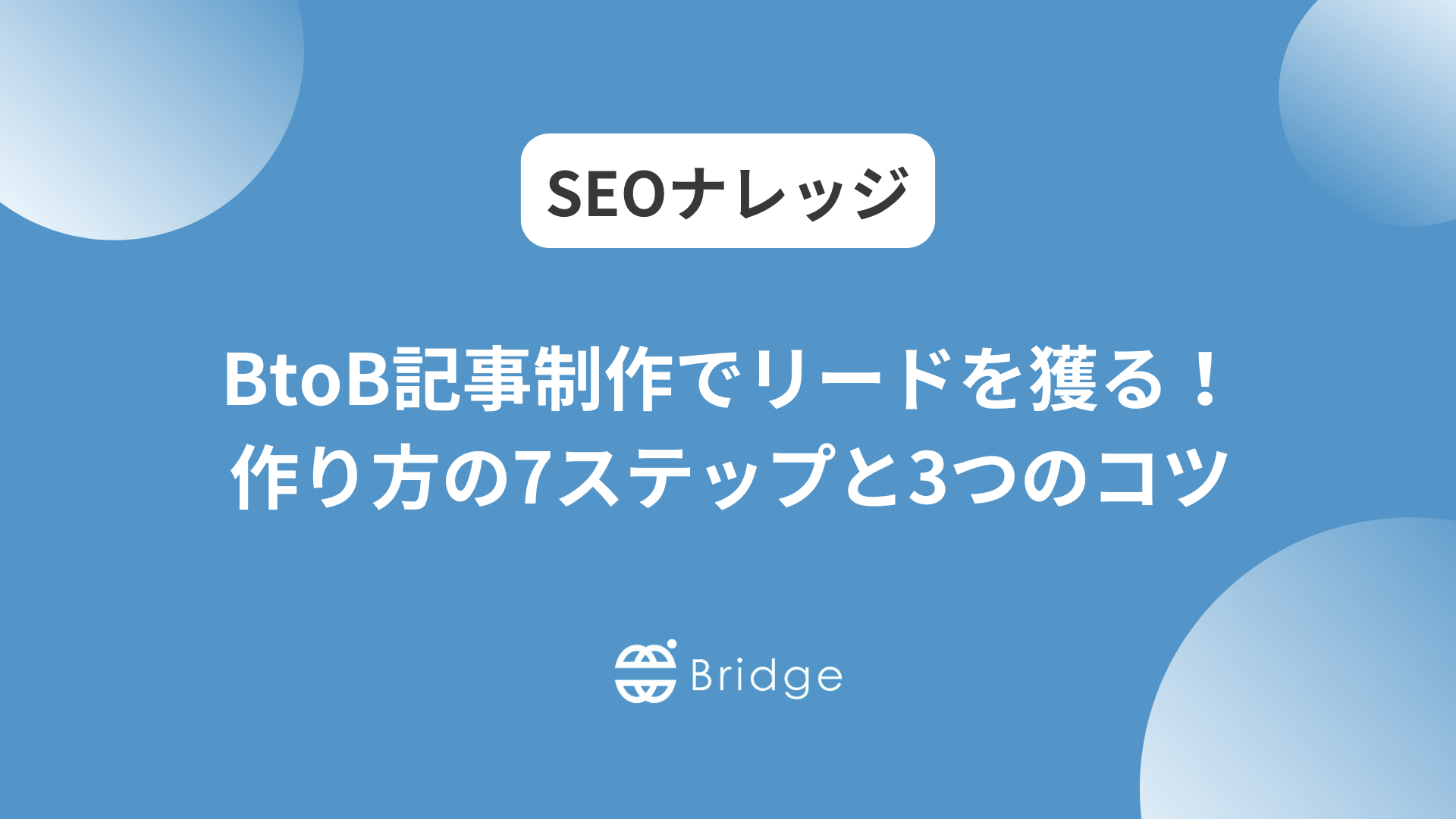
#SEOナレッジ
BtoB記事制作でリードを獲る!作り方の7ステップと3つのコツ
-
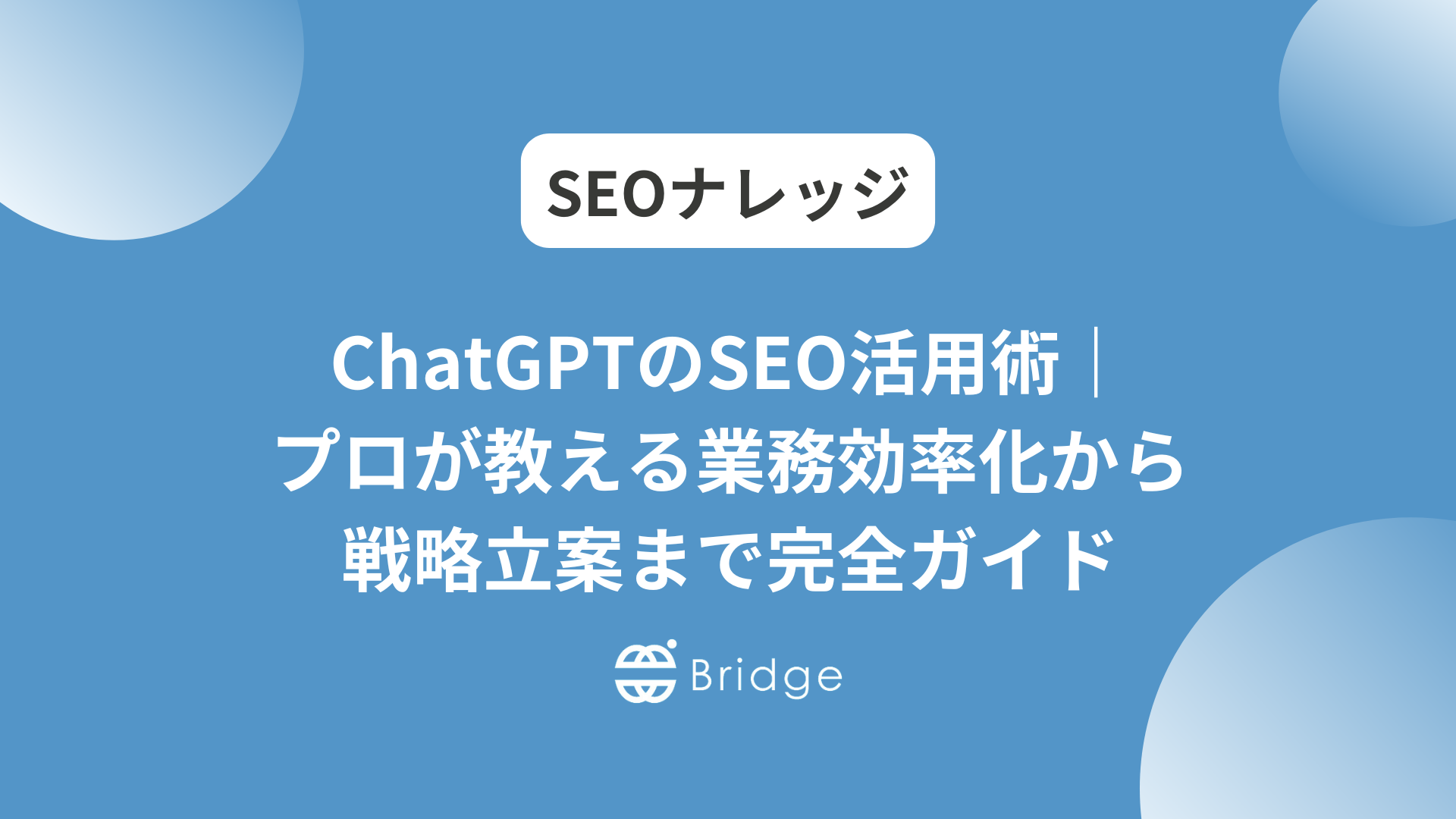
#SEOナレッジ
ChatGPTのSEO活用術|プロが教える業務効率化から戦略立案まで完全ガイド
