クエリファンアウトとは?Google AI検索の仕組みとSEOへの影響を解説

GoogleのAIモードは、なぜあれほど複雑な質問に、一度で的確な答えを返せるのでしょうか?その心臓部ともいえる技術が「クエリファンアウト(Query Fan-out)」です。
この記事では、「クエリファンアウト」という技術の仕組みを誰にでも分かるように解説します。さらに、この技術が今後のSEOやコンテンツ制作に与える本質的な影響と、私たちが今から備えるべきことまでを深く考察します。
この記事でわかること:
- クエリファンアウトの仕組み(分解・並列検索・統合)がわかる
- AIモードやRAGといった関連技術との正確な関係性がわかる
- これからのSEOコンテンツに求められる3つの要件がわかる
この記事の監修者
坂本理恵 株式会社Bridge 取締役COO
▼主な経歴
- 株式会社リクルート、株式会社サイバーエージェント出身
- 株式会社Bridgeを創業し、SEO事業、インターネット広告代理事業の立ち上げ〜グロースに従事
- AI×SEO関連のウェビナーにも登壇
▼関連リンク
https://x.com/rie151515
目次
クエリファンアウトとは?AIモードを支える「AIによる分業検索」
💡このパートまとめ
ユーザーの複雑な質問を、AIが複数の簡単な質問に分解し、同時に検索して答えを統合する技術。
まず、「クエリファンアウト」という言葉の核心的なイメージを掴みましょう。
Google検索におけるクエリファンアウトの役割
クエリファンアウトは、GoogleのAIモードやAI Overviewsといった、生成AIを活用した新しい検索体験を実現するための基盤技術です。従来の検索とは一線を画す回答精度を支える、まさに「AI検索の心臓部」と言えるでしょう。
一言でいえば「AIがあなたの代わりに何度も検索してくれる」仕組み
クエリファンアウトを非常にシンプルに表現するならば、それは「AIによる、超高速な分業検索」です。
あなたがこれまで、複雑な調べものをする際に「まずこれを調べて、次にあれを調べて…」と、何度も検索キーワードを打ち直していたはずです。クエリファンアウトは、その人間が頭の中で行っていた「検索の分解と再構築」というプロセスを、AIが瞬時に代行してくれる技術なのです。
AIモード、AI Overviewsとの関係性
ユーザーがAIモードで「京都で歴史を感じる2泊3日の旅行プランと、ベジタリアン向けの夕食」のような複雑な質問を投げかけると、AIが包括的な回答を生成します。
通常の検索画面においても、AI Overviewsが「AIによる概要」として要約した回答を生成してくれます。
このような回答を生成するために、裏側でGeminiのような大規模言語モデル(LLM)に「このようなプランを生成せよ」と指示を出すのが、クエリファンアウトの役割です。つまり、クエリファンアウトが優秀なアシスタントとして必要な情報を集め、Geminiが専門家として最終的な答えを組み立てる、という関係にあります。
AIモードについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
クエリファンアウトの仕組みを3ステップで理解する
💡このパートまとめ
「分解」「並列検索」「統合」の3ステップで、AIは人間を超える広範囲な情報収集を瞬時に行う。
それでは、クエリファンアウトの具体的なプロセスを、3つのステップに分けて見ていきましょう。
✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス
【結論】: 従来の検索が、一つの問いに対して一つの答え(検索結果リスト)を返す『シングルスレッド』だったのに対し、クエリファンアウトは、一つの問いを複数の問いに広げて同時に答えを探す『マルチスレッド』な検索です。この構造変化が、検索体験の質を根本から変えているのです。
Step1:分解(Decomposition):複雑な質問を単純な「サブクエリ」へ
まず、AIはユーザーから投げかけられた複雑な質問を、意味の塊(エンティティ)を基に、より単純で検索しやすい複数の「サブクエリ」に分解します。
Step2:並列検索(Parallel Execution):分解したサブクエリを一斉に検索
次に、分解して生成した複数のサブクエリを、従来のGoogle検索エンジンを使って一斉に、かつ並列で実行します。これにより、人間が一つずつ検索するよりも圧倒的に速く、広範囲な情報を集めることができます。
Step3:統合(Synthesis):集めた情報を基に、Geminiが最終的な回答を生成
最後に、それぞれのサブクエリで得られた検索結果(Webページの情報など)をすべて集約し、それを基にGeminiが最も適切で包括的な回答を一つの文章として生成します。
クエリファンアウトがSEOとコンテンツ制作に与える3つの影響
💡このパートまとめ
検索意図の多様化に対応するため、網羅的で信頼性の高い「課題解決型コンテンツ」がより重要になる。
この技術的な変化は、私たちコンテンツ制作者にどのような影響を与え、何を求めるのでしょうか。
影響①:単一キーワード対策から「トピック対策」へのシフト
クエリファンアウトは、Googleがユーザーの多面的で複雑な検索意図を、一度の検索で理解できるようになったことを意味します。
これにより、「京都 観光」のような単一のキーワードで上位表示されることの価値は相対的に低下します。代わりに、「京都旅行プラン」という大きなテーマ(トピック)に対して観光、食事、交通といった関連する複数の疑問に一つの記事で包括的に答える「課題解決型コンテンツ」が、AIにとって引用しやすい優れた情報源として評価されるようになります。
影響②:情報の「網羅性」と「信頼性(E-E-A-T)」の重要性が増大
AIは、複数のサブクエリから得られた情報を統合して、最も信頼できる「正解」を導き出そうとします。そのため、断片的な情報しか提供していないサイトよりも、一つのテーマについて多角的に、そして深く解説している網羅的なサイトが、情報源として選ばれやすくなります。
同時に、その情報が本当に正しいかを判断するために、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)がこれまで以上に重要なシグナルとなります。
影響③:構造化された「引用されやすい」コンテンツが有利に
AIが検索結果から情報を「引用」しやすいように、コンテンツを構造化しておくことが有効になります。具体的には、Q&A形式で見出しと回答を明確に分けたり、手順を番号付きリストで示したり、構造化データを用いてコンテンツの意味をAIに正確に伝えたりといった工夫です。
補足:RAG(検索拡張生成)との関係性は?
💡このパートまとめ
クエリファンアウトはRAGの「検索」部分を高度化したもの。両者は協調して動作する技術。
技術に詳しい方なら、「これはRAG(検索拡張生成)と何が違うのか?」と疑問に思うかもしれません。
RAGの基本的な仕組みのおさらい
RAGとは、LLMが回答を生成する際に、外部の知識データベースをリアルタイムで検索し、その情報を根拠として回答を生成する技術の総称です。
RAGについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
クエリファンアウトは、RAGの「Retrieval」プロセスの一部と解釈できる
この観点から見ると、クエリファンアウトは、Googleが自社の検索サービスにおいて実装している、RAGの「Retrieval(検索・取得)」プロセスを、より高度化させたものと解釈できます。一般的なRAGが単純な類似検索を行うのに対し、クエリファンアウトは質問を分解し、複数の検索を並列実行するという、より洗練された検索・取得を行っているのです。
どちらも「LLMに外部知識を与える」という目的は同じ
結論として、両者は競合する概念ではなく、「LLMの知識を外部情報で補強し、回答の正確性と鮮度を高める」という共通の目的を持つ、協調して動作する技術と理解するのが最も正確です。
まとめ:技術を理解し、未来の検索に適応するコンテンツを作ろう
今回は、GoogleのAI検索を支える核心技術「クエリファンアウト」について、その仕組みからSEOへの影響までを解説しました。
- クエリファンアウトの仕組み: ユーザーの複雑な質問を「分解→並列検索→統合」する、AIによる超高速な分業検索。
- SEOへの3つの影響: ①トピック対策へのシフト、②網羅性と信頼性の重要性増大、③構造化されたコンテンツの有利性。
クエリファンアウトの登場は、小手先のSEOテクニックの終わりを告げ、ユーザーが抱える複雑な課題に、いかに正面から向き合い、包括的な答えを提供できるかという、コンテンツの本質的な価値が問われる時代の始まりを意味します。
まずは、あなたの専門分野で最も包括的な「まとめ記事」が、クエリファンアウトによるAIの多角的な検索に耐えうる品質と網羅性を備えているか、見直してみることから始めてみましょう。
クエリファンアウトについてもっと詳しく聞きたいという方は下記よりお気軽にお問い合わせください。
Pick up
SEOナレッジのピックアップ記事
-

#SEOナレッジ
SEO記事作成代行会社・サービス27選!依頼する際の選定ポイントも紹介
-
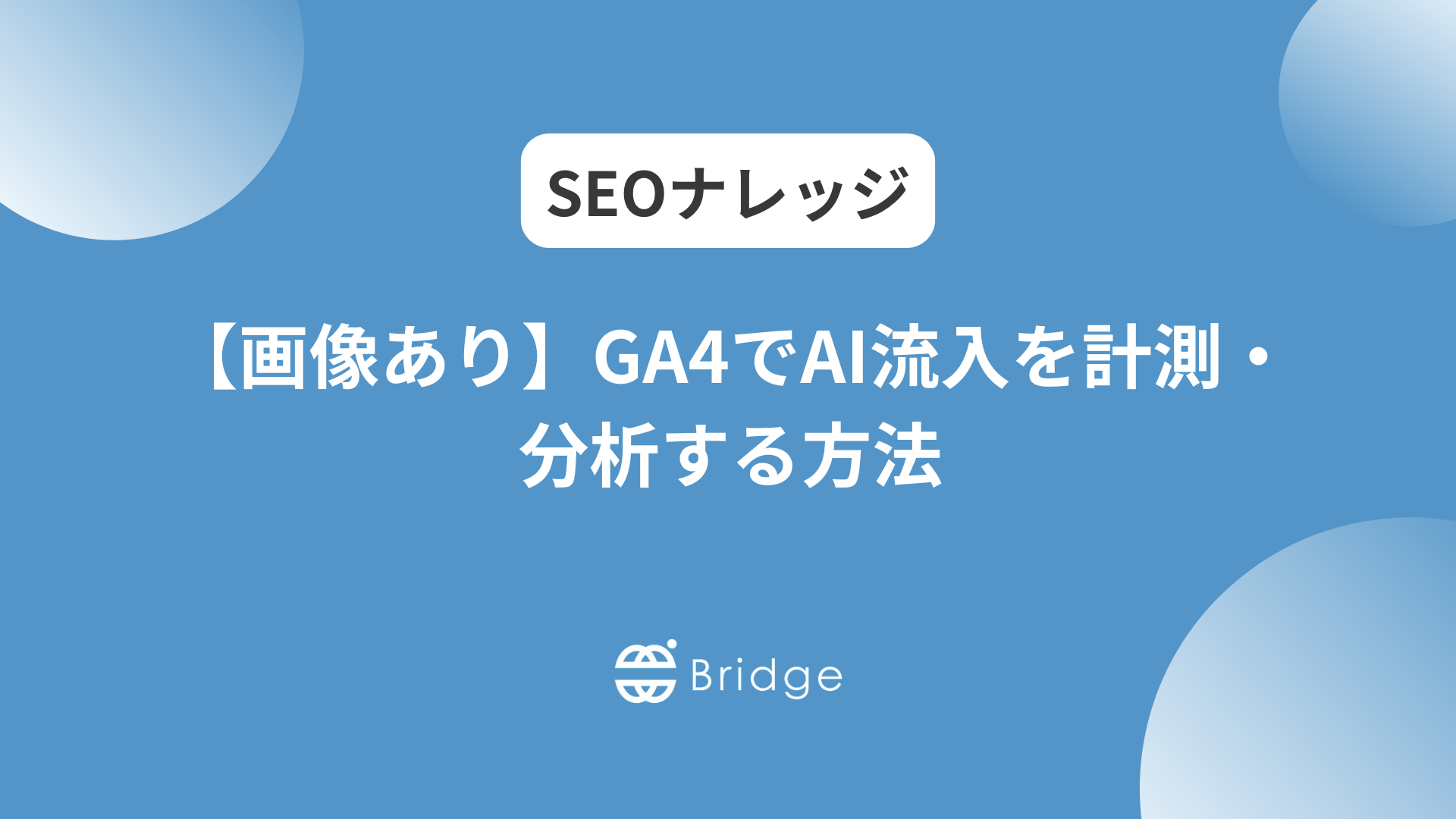
#SEOナレッジ
【画像あり】GA4でAI流入を計測・分析する方法
-
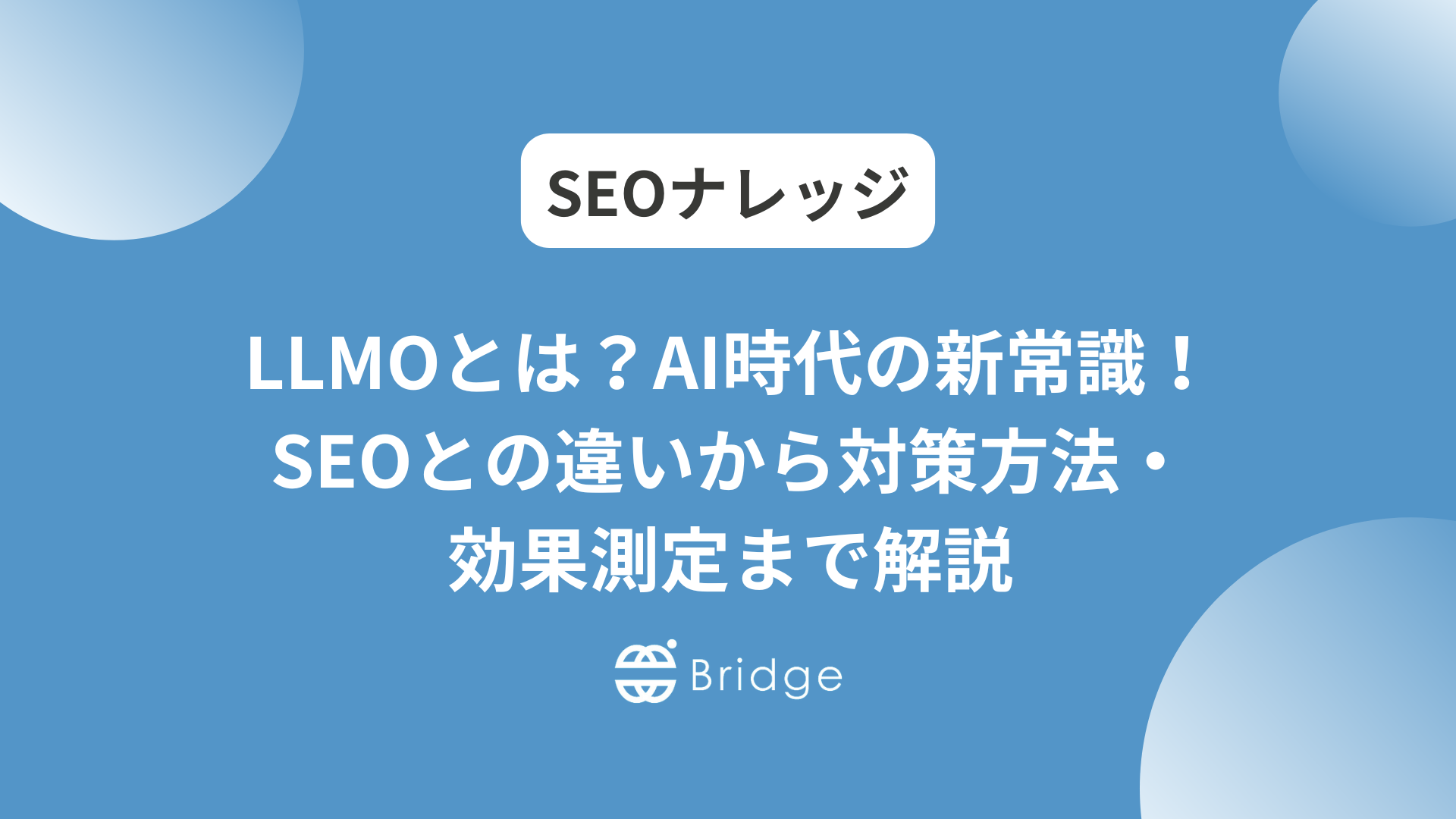
#SEOナレッジ
LLMOとは?AI時代の新常識!SEOとの違いから対策方法・効果測定まで解説
-
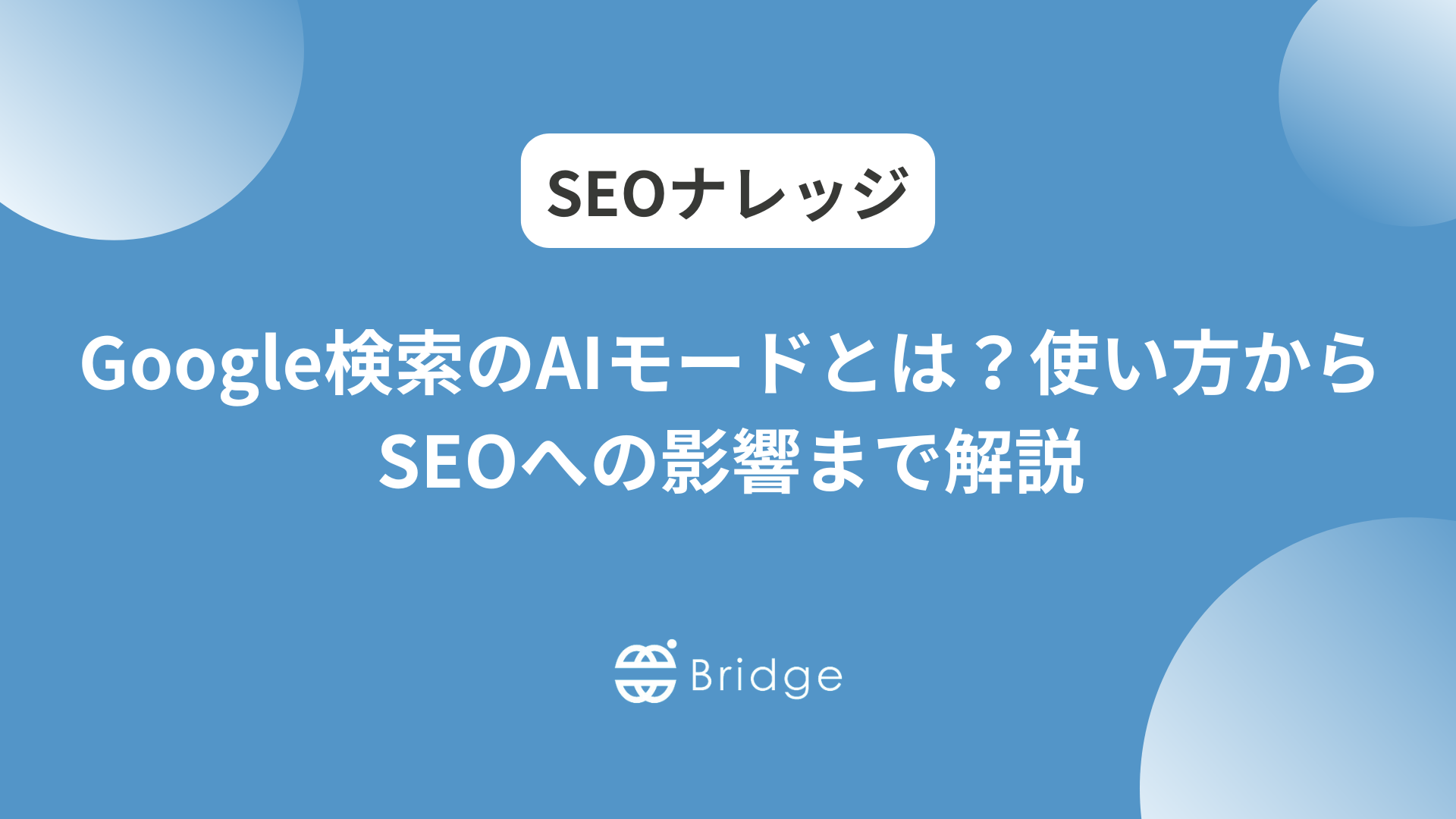
#SEOナレッジ
Google検索のAIモードとは?使い方からSEOへの影響まで解説
-
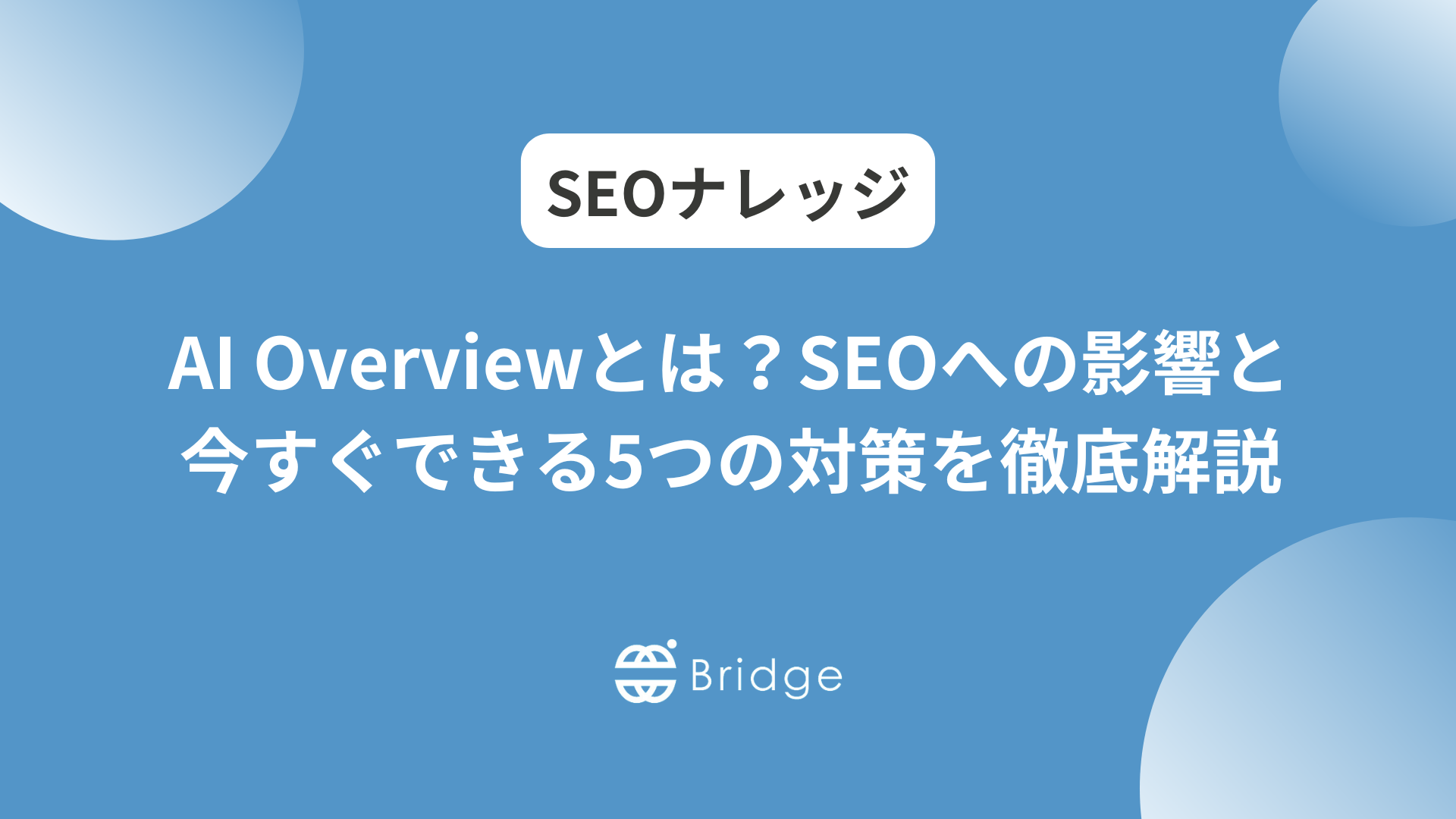
#SEOナレッジ
AI Overviewとは?SEOへの影響と今すぐできる5つの対策を徹底解説
-

#SEOナレッジ
AI記事作成ツール徹底比較|ChatGPT・Gemini・Claude、SEOに最適なのは?
-
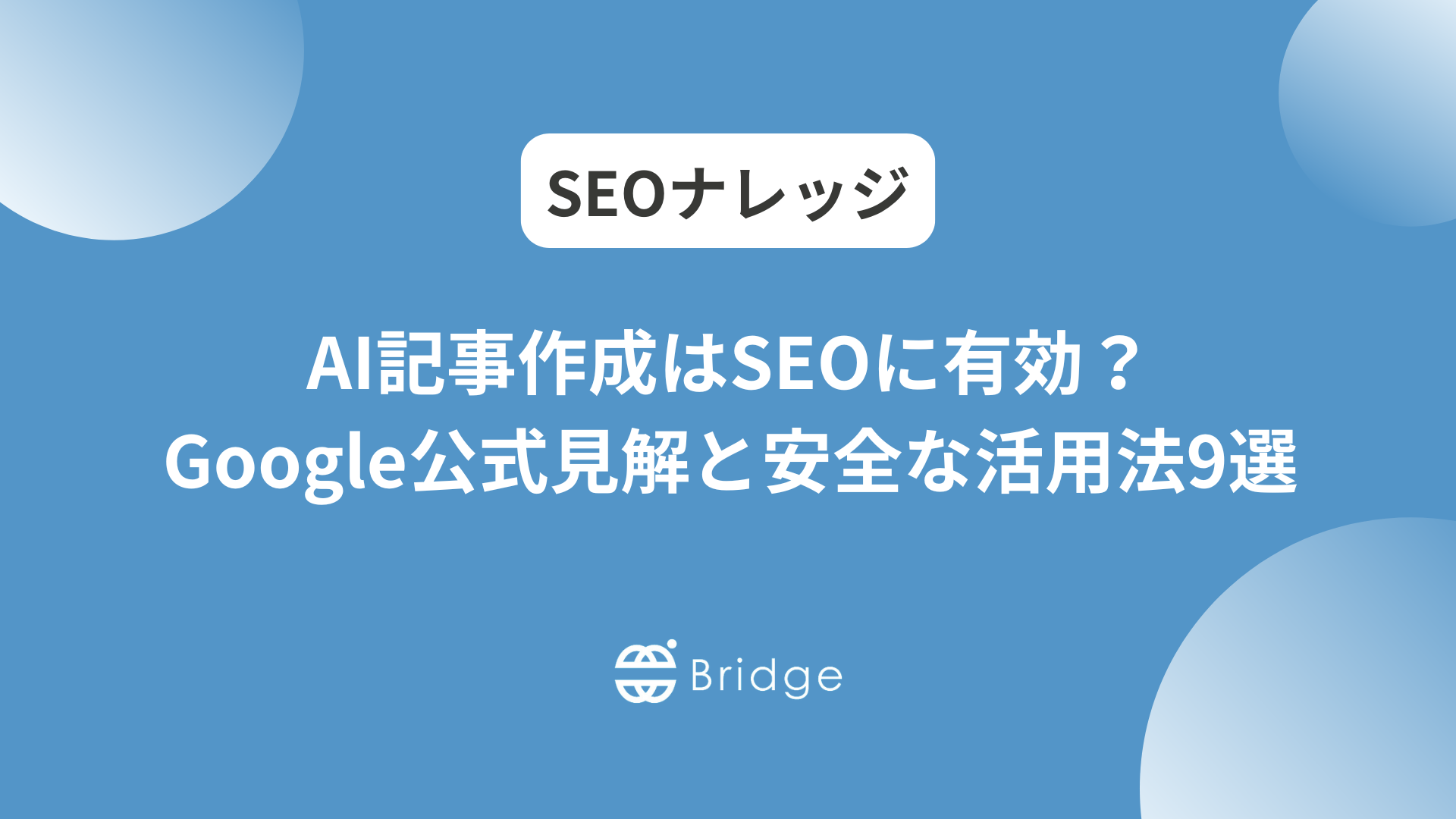
#SEOナレッジ
AI記事作成はSEOに有効?Google公式見解と安全な活用法9選
-
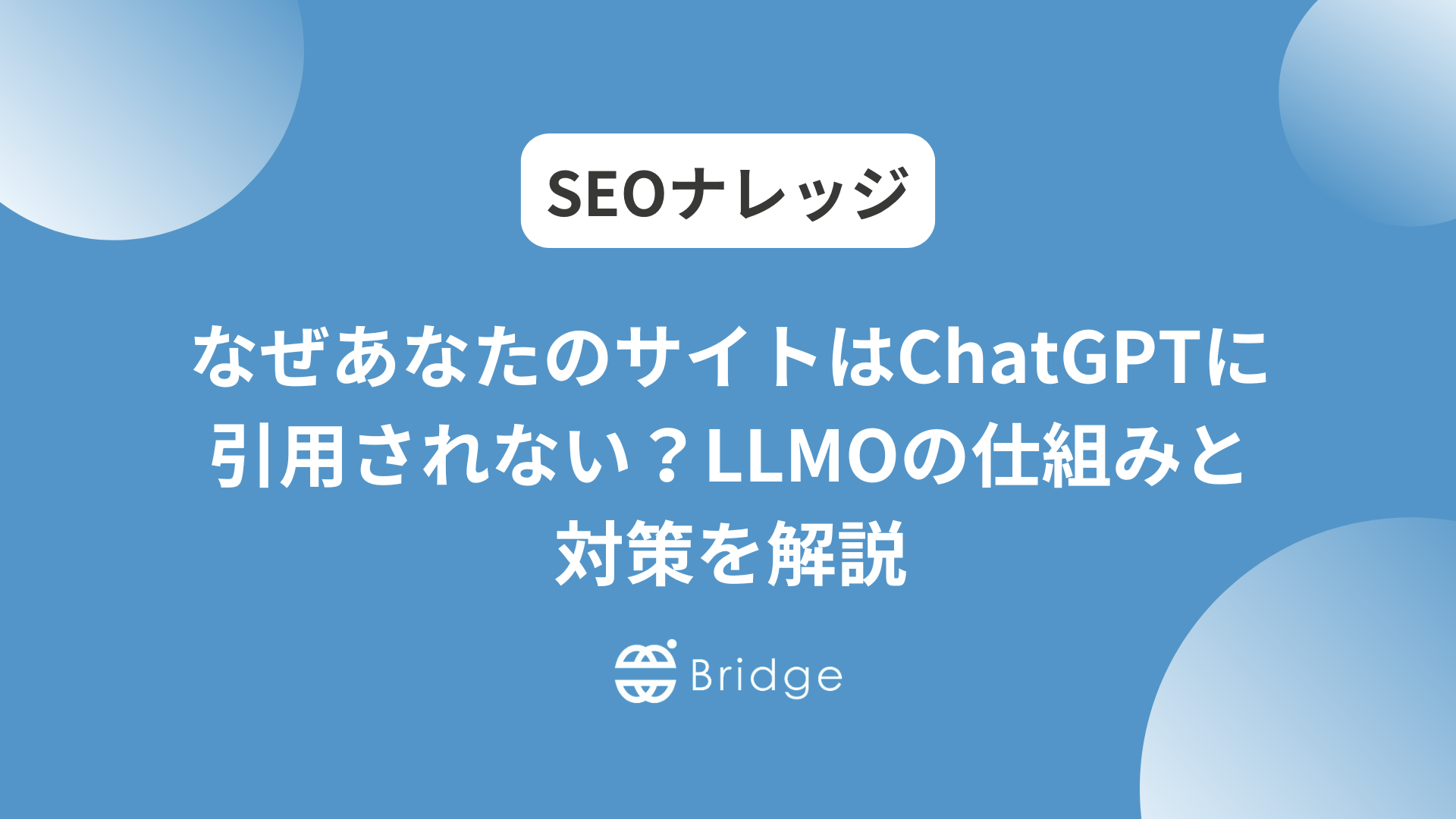
#SEOナレッジ
なぜあなたのサイトはChatGPTに引用されない?LLMOの仕組みと対策を解説
-
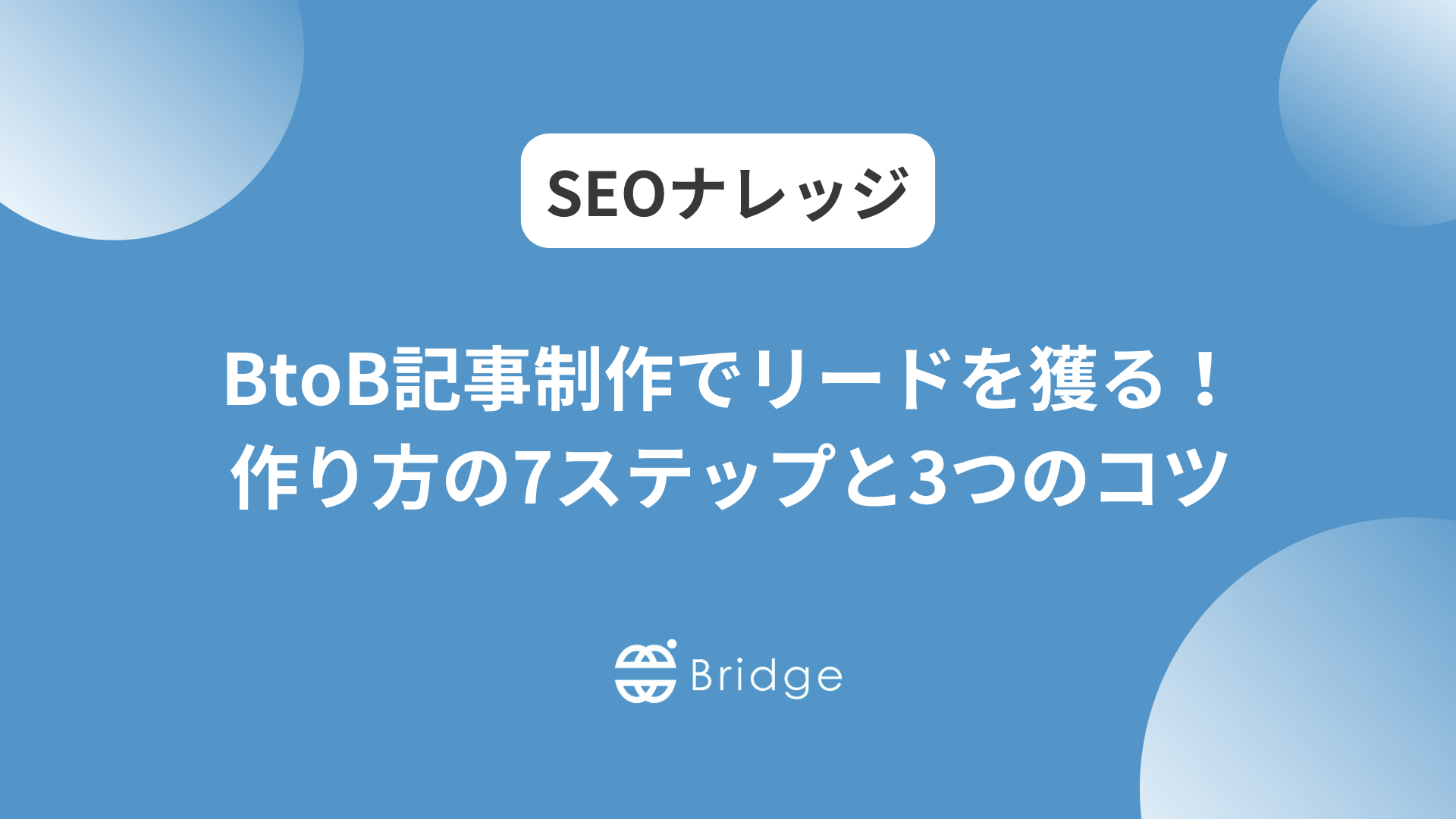
#SEOナレッジ
BtoB記事制作でリードを獲る!作り方の7ステップと3つのコツ
-
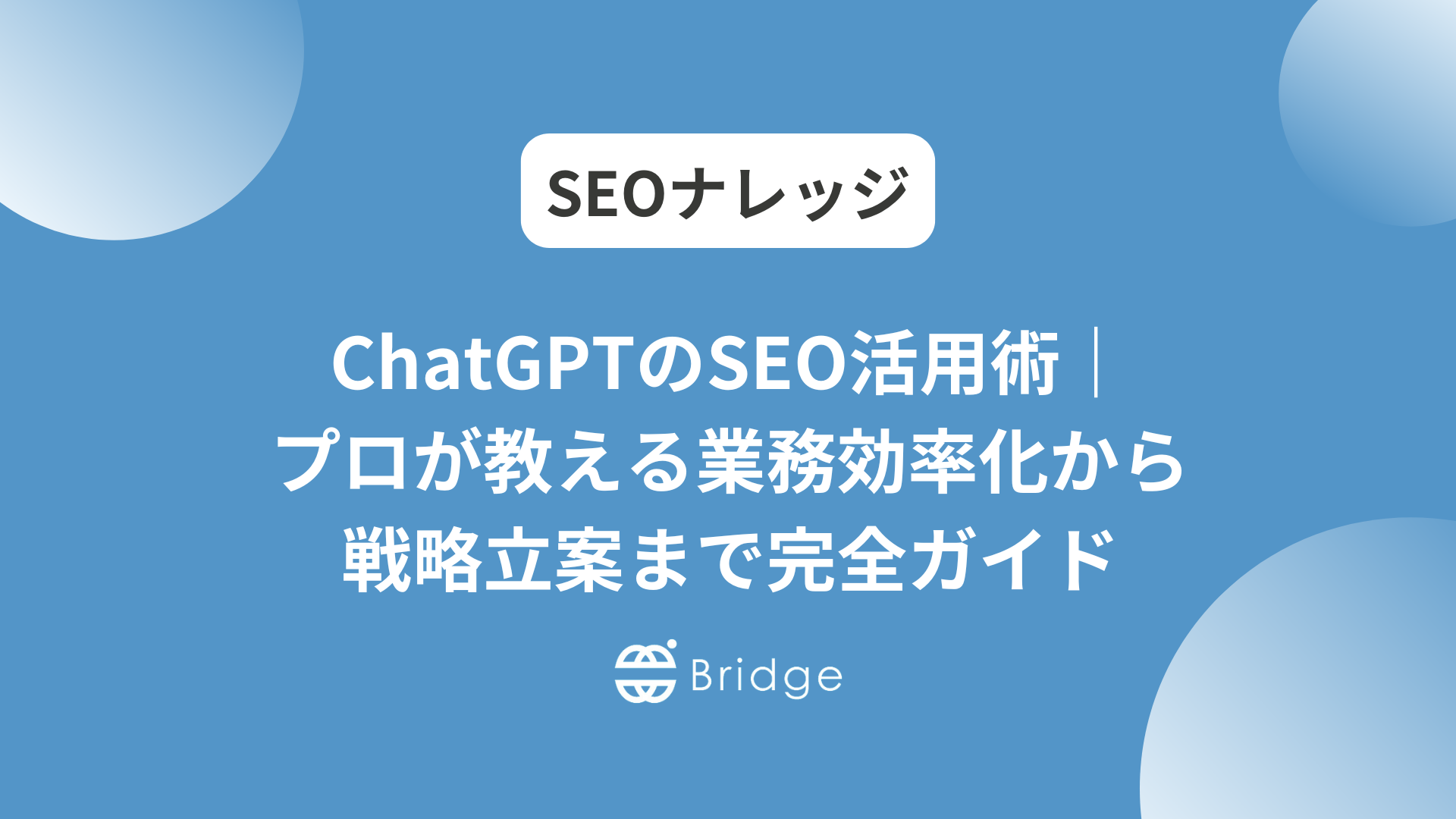
#SEOナレッジ
ChatGPTのSEO活用術|プロが教える業務効率化から戦略立案まで完全ガイド
